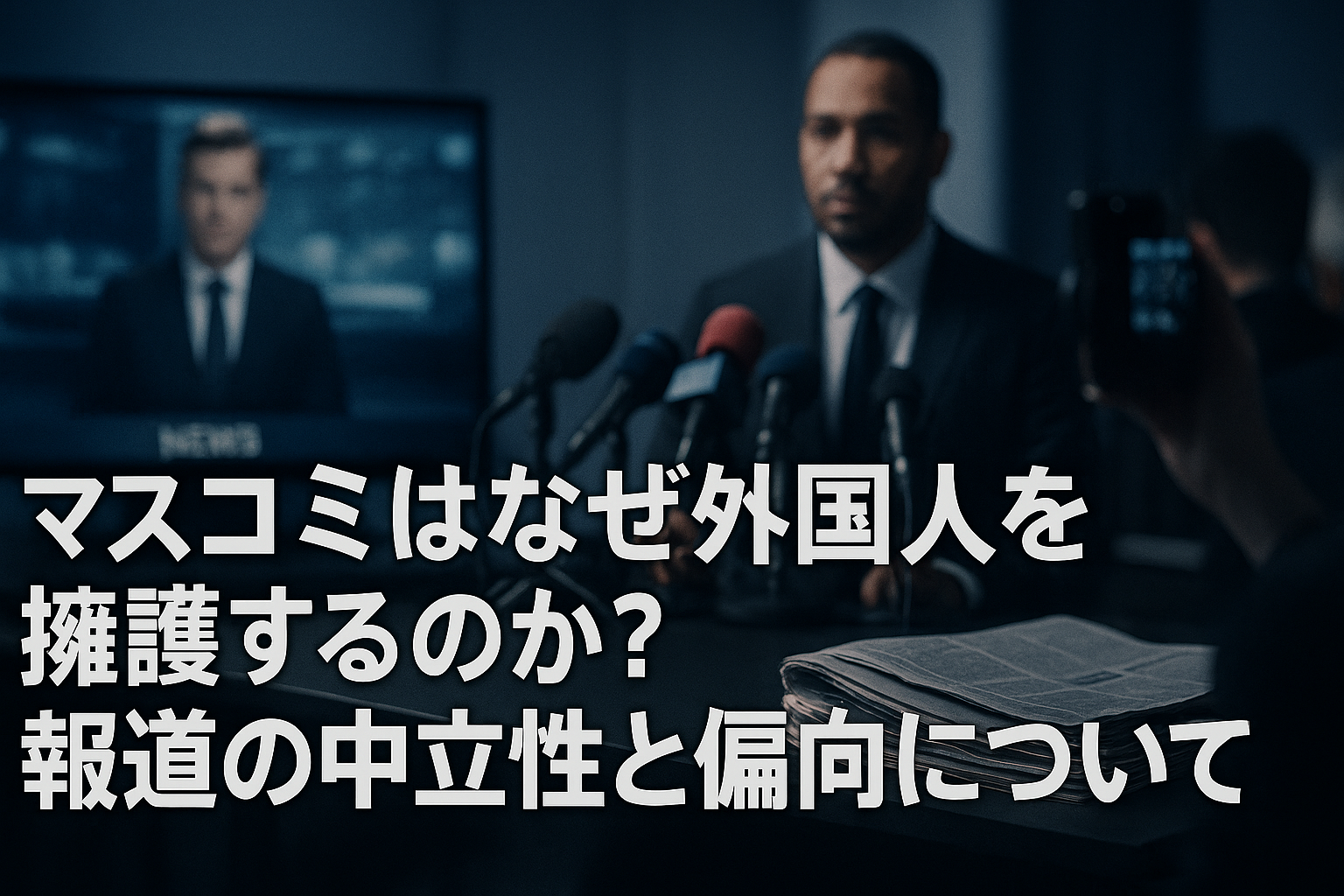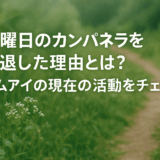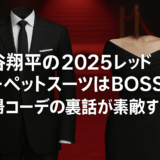テレビやネットニュースを見ていて、「あれ?なんだか外国人に優しすぎない?」と感じたことはありませんか?
SNSでは「マスコミが外国人を擁護しすぎてる」といった声も少なくなく、時に炎上の火種にもなっています。
では、なぜそう見えるのでしょうか?
本当に報道は偏っているのか?
それともそう見えてしまう“理由”があるのでしょうか?
この記事では、報道現場で重視される「多様性」の価値観や、放送法・スポンサーの影響、SNSとのズレまで、さまざまな角度から「マスコミと外国人報道の関係」を紐解いていきます。
読むことで、メディアへのモヤモヤが少しスッキリするかもしれません。
もくじ
マスコミはなぜ外国人を擁護するのか?
多くの報道を見て「マスコミは外国人に甘いのでは?」と感じたことがある人は少なくないと思います。
その背景には、報道現場が掲げる“多様性”の価値観や、社会的に求められる公平性への配慮があるようです。
今回は、報道における外国人擁護の構造について、具体的な事例とともに考察していきます。
次に、実際に現場で語られる「多様性の価値観」が、どのように報道内容に影響しているのかを見ていきます。
報道現場で語られる“多様性”の価値観とは
報道現場では、「多様性の尊重」がひとつの基本姿勢とされています。
これは国籍、人種、性別、宗教などの違いを偏見なく取り上げ、差別を助長しないための配慮です。
たとえばTBS系『報道特集』では、外国人政策をめぐる参政党の主張を取り上げた際、「排外主義への不安」や「選挙ヘイトを許さない」といった表現がテロップで使われました(引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/51c963a5f5cc3ad840856058ef357e6541ace701)。
こうした表現は、外国人差別を抑制するという目的がある一方で、視聴者の中には「過剰な擁護」と受け取る人もいるようです。
また、アナウンサーの発言も注目されました。「自分の一票が、身近な外国人の暮らしを脅かすかもしれない」というコメントが印象的でした(引用同上)。
このような表現は、外国人と共に暮らす社会の現実を伝える意図がある一方で、特定の方向へ意識を誘導していると受け取られる場合もあります。
報道がどの立場に立つかは非常に繊細な問題で、視点によって「擁護」と感じるか「中立」と感じるかが分かれるところです。
続いては、こうした報道が「偏向」だと感じられる背景にある、SNSや放送倫理の問題について掘り下げていきます。
偏向報道の実態と「公平性」の崩壊
「報道は中立であるべき」と多くの人が思っている一方で、実際のニュースを見ると偏りを感じることがあります。
とくに外国人に関する話題では、擁護的な表現や、特定の意見に寄った解説が目立つこともあり、SNSでは「偏向報道だ」と批判されることも少なくありません。
ここでは、放送される情報とされない情報、その差がSNSでどのように受け止められているかを見ていきます。
まずは、「報道しない自由」という概念とSNSユーザーの反応について取り上げます。
報道しない自由とSNSでの反発
報道機関には「表現の自由」と並び「報道しない自由」も存在すると言われています。
つまり、ニュースとして取り上げる・取り上げないの判断は、あくまで編集権の範囲内とされるため、たとえ事実でも放送されない場合があります。
しかしこの“選択”が、世論と乖離する原因にもなっているようです。
最近では、外国人による犯罪やトラブルがネット上で話題になっても、地上波ニュースでは取り上げられないケースが続き、「なぜ報道しないのか?」という声が上がっています。
SNS上では「#報道しない自由」などのハッシュタグが広まり、ニュースに取り上げられなかった事件をユーザーが自ら発信する流れが見られます。
例:X(旧Twitter)にて「#報道しない自由」を検索:https://x.com/search?q=%23報道しない自由
一方で、報道機関側が自主的に報道を控える理由として、「差別を助長する恐れがある」「事実確認が困難である」といった事情も存在します。
つまり、報道されない理由が「意図的な隠蔽」ではなく「慎重な判断」である可能性もあるため、一概に断定することはできません。
とはいえ、SNSでの情報流通スピードが上がった現代では、報道されない情報ほど疑念が生まれやすくなっており、「テレビを信じられない」という風潮にもつながっているようです。
次は、報道の背後にある「スポンサー」や「テレビ局の戦略」が、内容にどのような影響を与えているのかを深掘りしていきます。
テレビ局のスポンサーとイメージ戦略の関係
テレビ局の報道姿勢には、視聴者だけでなく、スポンサー企業の存在が大きく影響していると指摘されています。
スポンサーは番組制作費の大部分を支える存在であり、その意向に逆らうような報道は、放送局にとってリスクになることもあります。
そのため「スポンサーにとってマイナスイメージになる内容は避ける」という“自主規制”が行われるケースもあるとされています(引用:https://www.nhk.or.jp/bunken/research/focus/f20140701_2.html)。
特にグローバルに展開している企業がスポンサーである場合、多文化共生やダイバーシティといった価値観が尊重されやすくなります。
その結果として、外国人に関する報道では「差別的」と捉えられる表現を避けたり、批判的な論調が控えられたりする可能性があるとも考えられます。
また、テレビ局自身も「人権を尊重する企業姿勢」や「先進的なイメージ」を保つため、あえて外国人に配慮した報道方針をとる場合もあるようです。
こうした背景があるため、視聴者が「報道が外国人寄りだ」と感じる瞬間が生まれるのかもしれません。
とはいえ、全ての報道がスポンサーに配慮した結果とは言い切れず、編集部内での議論やジャーナリズムの信念が反映されたものであるケースも当然あります。
報道内容は、視聴率だけでなく「どの企業が見ているか」によっても変化する複雑な構造を持っていると言えるでしょう。
次のパートでは、外国人と日本人で報道の扱いに差があるのか、具体的な事例を通じて検証していきます。
外国人と日本人で報道の扱いが違うのはなぜ?
テレビや新聞で報道される内容を見て、「外国人の事件はあまり取り上げられないな…」と感じたことはありませんか?
実際にSNSでは、こうした報道傾向に違和感を覚える声がたびたび上がっています。
このセクションでは、報道される側に“国籍による差”があるのかどうか、その理由や背景を事例とともに探っていきます。
まずは、「外国人の事件報道が少ない」と言われる理由について見ていきます。
外国人の事件報道が少ない理由
「外国人による事件が報道されない」と感じる人がいるのは事実です。
SNS上では「外国人だと実名が出ない」「そもそも事件自体がニュースで扱われない」といった声がよく見られます(例:https://x.com/search?q=外国人%20報道されない)。
こうした認識が生まれる背景には、いくつかの理由があるようです。
まず、報道機関は報道倫理に則り、事実確認が不十分な場合や、差別を助長する可能性があると判断した場合は、意図的に報道を控えるケースがあります。
特に「国籍」や「出自」によって当人の行動を過度に強調することは、不当な偏見を生むおそれがあるとされており、慎重な判断が求められています(参考:日本新聞協会 編集倫理綱領 https://www.pressnet.or.jp/about/ethics/)。
また、警察発表が「国籍非公表」となる場合もあり、その場合メディアも報じる情報に制限を受けます。
そのため、「外国人だから報じない」というよりも、「情報が不明確だから報じにくい」といった事情がある可能性も考えられます。
一方で、事件性が高く社会的影響が大きい場合には、外国人であっても報道される事例は存在しています。
ただし、こうした報道が相対的に少なく見えるのは、日本人に比べて人数が少ない外国人の事件発生件数が単純に少ないためとも考えられます。
報道機関が「誰が」「どこで」「何をしたのか」を伝える中で、どの情報を強調するかのバランスは非常に難しく、報道方針によっても差が出る部分です。
次は、「マスコミに忖度や政治的圧力があるのか?」という視点で、放送法やBPO(放送倫理・番組向上機構)の役割を整理していきます。
マスコミに忖度や政治的圧力はあるのか?
ニュースやテレビ番組を見て、「この発言、本当に自由に言ってるのかな?」と思うことはありませんか?
特定のテーマになると急に報道が減ったり、逆に一方的な論調が目立ったりすると、視聴者としては「何か圧力でもあるのでは?」と感じてしまいますよね。
ここでは、マスコミと政治や権力との関係に焦点を当て、報道の自由がどう守られているのかを見ていきます。
まずは、そのベースとなる法律「放送法」と、番組内容のチェックを行う「BPO」の仕組みを押さえておきましょう。
放送法とBPOの仕組みを知ろう
日本の放送には「放送法」という法律があり、その第4条では以下のように定められています。
- 政治的に公平であること
- 報道は事実をまげないこと
- 意見が対立する問題については、多角的に論点を明らかにすること
(出典:総務省 放送法解説 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/broad01.html)
つまり、テレビやラジオで放送されるニュースや番組には、明確なルールがあるということです。
このルールに反していると感じた場合、誰でも「BPO(放送倫理・番組向上機構)」という第三者機関に申し立てを行うことができます。
実際、2024年7月にはTBS『報道特集』の放送に対して、参政党が「著しく公平性を欠いている」としてBPOに意見を提出しました(引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/51c963a5f5cc3ad840856058ef357e6541ace701)。
ただし、BPOはあくまで勧告機関であり、法的な強制力はありません。
つまり、政治的圧力に直接屈して報道が変わることは制度上はないはずですが、「スポンサーや政治的立場に“忖度”した結果、偏った放送になっているのでは?」と受け止められることはあるようです。
また、メディア企業によっては、政治的な立場や社内方針に基づき、特定の主張を強く押し出すこともあり、その違いが「偏向」と感じられる一因にもなっています。
次は、「報道方針は誰がどう決めているのか?」という内部のプロセスについても掘り下げてみましょう。
報道方針は誰が決めている?
テレビ局の報道内容が「どのように決まっているのか?」については、あまり知られていないかもしれません。
報道の方針は、基本的には各放送局の報道局にある「編集会議」や「デスク会議」で日々決められています。
そこでは、どのニュースを扱うか、どのような順番で放送するか、コメントをどう構成するかなどが細かく議論されます。
番組ごとにチーフプロデューサー(CP)や報道局長クラスの人が最終判断を下すことが多く、記者やディレクター、キャスターの意見も取り入れられることがあります。
ただし、あくまで最終的には「会社の方針」に沿うかたちになるため、社の方針や取締役会、あるいはスポンサーの意向が間接的に反映される場合もあります。
また、局ごとに「報道ガイドライン」や「倫理綱領」といった内部ルールが存在し、それに反する内容はあらかじめ排除される仕組みもあります(例:NHKの番組基準 https://www.nhk.or.jp/bunken/about/program-guideline.html)。
一方で、放送直前に社会的な出来事が発生したり、SNSで炎上したトピックが急浮上したりすることで、放送内容が急遽変更されることもあり、その柔軟性も特徴的です。
つまり、報道は完全なトップダウンでも、完全なボトムアップでもなく、社内の複数層の意見を反映しながら動いているというのが実態です。
ただし、視聴者から見たときに「誰が決めているのか」が見えにくいため、不信感や疑念が生まれやすいのも事実です。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
- マスコミが外国人を擁護しているように見える背景には、「多様性」や「共生」の価値観がある
- 報道には「しない自由」も存在し、視聴者との認識にズレが生まれやすい
- SNS上では「報道されないこと」が反発を呼び、信頼低下の一因に
- スポンサーや企業イメージも、報道内容に間接的に影響を与える場合がある
- 外国人の事件が少なく見える理由には、国籍を伏せた報道や件数自体の差がある可能性も
- 放送法やBPOなど、報道の公平性を担保する枠組みも存在している
- 最終的な報道方針は、テレビ局の編集会議や経営層、内部基準によって決まる
これらを通じて、「なぜ外国人擁護と見える報道がされるのか?」という疑問に対し、さまざまな視点からの理解が深まったのではないでしょうか。
ニュースを受け取る側である私たちにも、情報を多角的に見て判断する力=メディアリテラシーが求められています。